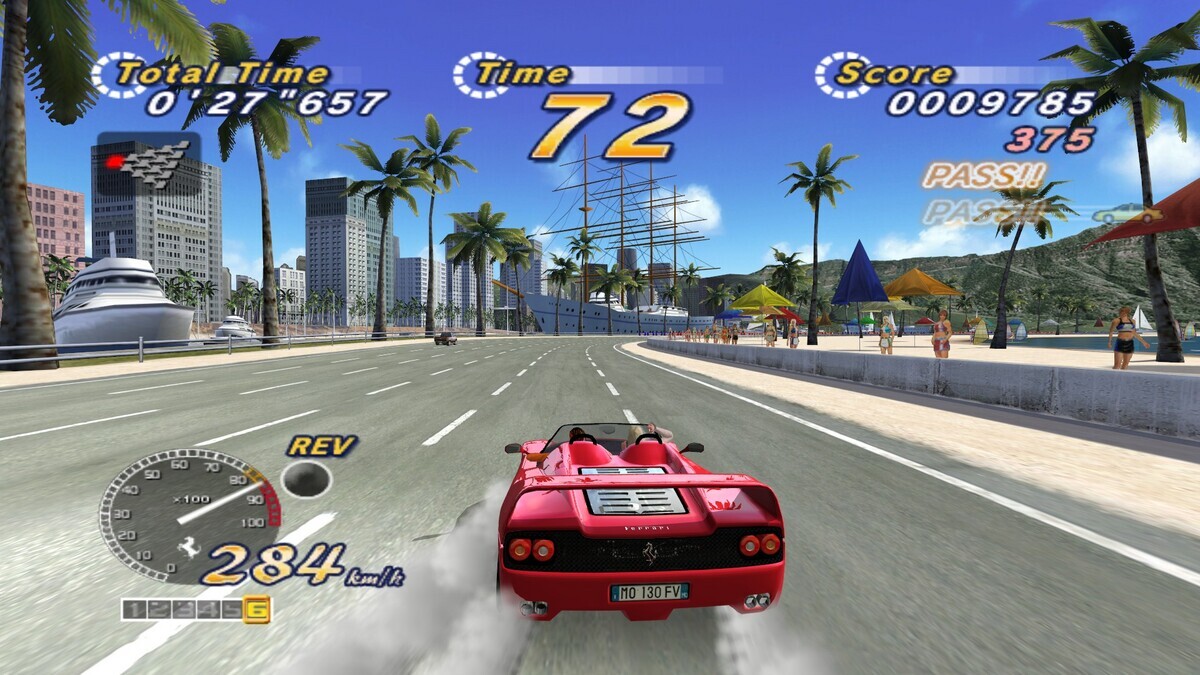戦国時代に日本に渡来し織田信長に小姓として仕えたという黒人「弥助」。本能寺の変で明智光秀に捕らえられ南蛮寺に送られてからの消息は定かではないという、波乱万丈かつ曖昧なその経歴から物語を作りやすく扱いやすい人物像のためか、創作物において何度か登場したりモチーフにされたりしてきたが、UBIソフトのゲーム「アサシンクリード」シリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」でもそんな彼を主人公の一人として発表したところ海外を中心に炎上。
元々海外のゲーム会社はポリコレ意識が高いというのもあってそれ目的で無理やり黒人を入れたのではないかと疑われたり、UBIソフト広報も「弥助は史実の侍」と言ってしまったり(正確には「弥助は史実の"人物"」と言いたかっただけで、単に侍とかの定義がよくわかってない可能性も高い)と歴史を扱ってきたシリーズなのに歴史改変を行っている!と荒れているが、アサクリシリーズ自体「DNAを通して先祖の記憶を読み取り、現代社会を裏で操るテンプル騎士団が持つという秘宝の在処を探る」なんていうトンデモファンタジーなストーリーのゲームが史実に忠実かどうかとかなんて今更議論にすることなのか!?とか、和ゲー(主にというかほぼコエテクゲーだけど)ですら誇張した表現で登場してきてそこから勝手な弥助像を作り上げる人だっているだろとか、自分もポリコレそのものは大嫌いとはいえ史実や実在の人物をモチーフとした他のフィクションに言及しないのはダブスタとも思うので逆に反発意見の方に色々ツッコミを入れたくもなる。
でも、「桜と柿と田植えが同じ時期に映っている映像」という四季の無さはフィクション以前の問題なんで指摘するべきだろ。
そんな騒動が続いていたが、東京大学で歴史学を専攻しているという日本人の「Kenji Yamamoto」(@Samurai_KenjiYa 既に鍵垢にして逃亡)なる人物がTwitter(旧X)において、「アサシンクリードの公式に"弥助は侍じゃない"と言っていたらブロックされた」と騒ぎ立て始める。

もちろんアサクリ シャドウズに批判的な人たちはこの話にすぐさま反応し始めたものの、どうもこの「Kenji Yamamoto」なる人物が胡散臭いと気づく人が何人か現れる。
というのも、東京大学にその名と同じ人物が所属しているという情報はなく、ジョー・バイデンのことを"俺たちの大統領"と言ってしまったり、日本人を名乗る割には日本語が怪しく機械翻訳に頼っているような返答をしてきたり、魚拓から調べると過去に「Garrett Barnes」という名前を設定していた経歴があることが見つかったためだ。
このような検証がなされた後はもちろん「Kenji Yamamotoは日本人じゃない。ただの白人デブだ」という反応が多くなっていったが、渦中のKenji Yamamotoは以下のように返答。

皆、私の事をKenjiを"演じてる"といってるが、この前は"Garrett"を演じてたんだ。アメリカ人とアメリカの政治を議論するためにアメリカ人に成りすましてたんだ。
実験は大成功だったよ。
という物凄い頭の悪そうな実験(になってない)をしていたと明かし、何故かはよくわからないけど自身の痛い過去ツイを消して鍵をかけて逃亡してしまう。
ブロックされた本当の内容はすぐには確認することはできないが、UBI側が批判意見を受け付けない一方的な対応をしていたとしていたとしても、わざわざ国籍を偽って指摘されたら苦しい言い訳を述べて逃亡した後ではメンドクサイ人間がいたからブロックしたまでという印象しか与えない。「弥助は侍じゃない」という身分の偽りを指摘している人間が、自身の身分を偽っているとかどういうことやねん。
そして、批判している人たちは身分を偽ったり平気でうそをつく、人種差別主義者が騒いでいるだけ、と批判グループ全体でそういう目で見られてしまう。
しかし、素性や実績がわからない人間でも自称専門家のみならず異邦人という肩書があるだけで権威のある人間が言った言葉の様に聞こえるという現象は、日本だけでなく世界共通の認識だったんだな。だからこそ批判をするだけなら偽る必要性がないにも関わらずわざわざ日本人なんて名乗っちゃって自信を大きく見せようとする。